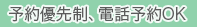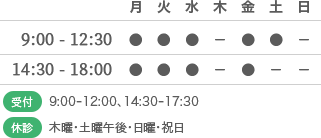加齢黄斑変性とは、黄斑の年齢変化によって起こる病気です。黄斑とは、目の奥にある光を受容する「網膜」という膜の中央部にある部分です。
黄斑は視力と関係する重要な部位で、ここに病気が起こるとものがゆがんで見えたり、見ようとする部分がよく見えなくなったり、視力が低下したりします。
黄斑に起こる病気には様々なものがありますが、加齢黄斑変性はその一つで高齢者の視覚障害の原因となります。網膜のさらに奥にある脈絡膜から新生血管といった新しい血管が発生する「滲出型加齢黄斑変性」と、網膜の細胞が徐々に傷んで萎縮する「萎縮型加齢黄斑変性」とがあります。
ゆがんで見える病気には、加齢黄斑変性以外の疾患もあるため、検査で確認することが必要です。
日本では、滲出型加齢黄斑変性が多く、萎縮性加齢黄斑変性は比較的稀とされています。
原因
加齢黄斑変性の原因には次のようなものがあります。
- 加齢
- 高血圧
- 肥満
- 喫煙
- 高脂肪食
- 太陽光
- 遺伝
日本では以前は加齢黄斑変性は頻度が低いとされていましたが、生活様式の欧米化と高齢者の増加に伴って患者数が増えていると言われています。
主な症状
ゆがんで見える、見たい部分がちょうど欠けて見えない、黒く見える、色がわかりにくい、ものが欠けて見える、といった症状がみられます。
加齢黄斑変性の検査
視力、眼圧検査のほか、眼底検査やOCTといった網膜の断層写真を撮る検査が行われます。その他、血管の状態を把握するためにOCTアンギオグラフィーという血管撮影や、蛍光眼底造影検査を行うことがあります。
※蛍光眼底造影は当院では行っておりません。
検査の際には、散瞳といって瞳孔を広げる点眼を行います。
瞳孔を広げると個人差はありますが4~5時間程度はかすみやまぶしさ、ピントが合わないといった症状が出ますので、回復するまで車やバイク、自転車の運転はできません。また、パソコンやスマホも見えにくくなります。運転でのご来院はお避け下さい。
治療法
抗VEGF療法(滲出型加齢黄斑変性)
VEGF(血管内皮増殖因子)が脈絡膜の新生血管を成長させますが、目の中にあるVEGFの働きを抑える薬を眼内に注射する方法です。新生血管や、網膜のむくみを改善させます。
抗VEGF療法は一般的に導入期には1か月に1回、3~4か月にわたり連続して治療を行い、その後は少し間隔を開けて治療を継続する維持期に入ります。
一度腫れてしまった網膜は機能が落ちやすく、視力の回復が困難なことも珍しくありません。視力をなるべく維持するための治療と考えていただくのがよいでしょう。
そのほかの治療法
光線力学療法(PDT)といって、光に反応する薬剤を注射してその薬剤が新生血管に到達したときにレーザーを照射する方法があります。比較的稀な治療法で、当院での取り扱いはありません。